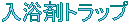 任務の帰り道、今回スリーマンセルを組んだ仲間の雑談が、聞くつもりはなくてもカカシの耳に入ってきた。 「テンゾウって入浴剤とか使わない?名湯ばっかりが揃ってる良い品物よ」 「え、いや…僕は」 元暗部が1人と、現役暗部が2人。 自分で言うのも何だが、こんな贅沢な顔ぶれで任務に就ける事なんて滅多にない。 「そう?お歳暮で貰ったんだけど、うちは子どもがいるから使わないのよね…」 そう呟いた夕顔が、ちらりとカカシに視線を送ってきた。 しかし、ふっ、と小馬鹿にしたように鼻で笑い、すぐにテンゾウに向き直る。 今回は表の任務なので、誰も暗部の面をつけていない。 そのために、いちいち表情がわかりやすい。 「あんた、使いそうな人に心当たりない?」 「そう言われましても…」 夕顔とテンゾウでは、夕顔の方が年下だ。 でも、暗部への入隊は夕顔の方が早かったので、テンゾウは夕顔に対して敬語を使っている。 「あ!そういえばカカシ先輩、前に温泉がどうのって言ってませんでしたっけ!」 急にテンゾウに会話の矛先を向けられて困惑する。 「オレが…?」 温泉なんて、カカシは特に興味はない。 いつそんな話をしたのだろう。 そう思って記憶を辿ると、大して時間も掛からずに思い出した。 イルカだ。 ふとイルカがどこどこの温泉に行ってみたいと言っていたのを思い出した時に、テンゾウに所在地を尋ねた事があった。 そんな他愛ない話を、テンゾウもよく覚えていたものだ。 「温泉に興味があるなら貰ったらいかがですかっ」 テンゾウが縋るような目で見つめてくる。 このままでは、テンゾウが入浴剤を押し付けられる事が明白だからだろう。 別にテンゾウを助ける義理はないが、悪い話ではないなと思った。 だって、イルカに渡したら喜んでくれそうだ。 以前イルカの家で、洗面所に入浴剤が置いてあるのを見掛けた事もあるし。 ついでにその時、乳白色のお湯に入ったイルカを想像して、人知れずに興奮した事まで思い出した。 「うん。入浴剤、オレにちょうだい」 殊勝なカカシの台詞に何かを感じたのか、夕顔が訝しむような視線を寄越してきた。 後輩の2人には、報告書は提出しておくと恩を着せておいて、堂々と報告書の提出権を獲得した。 外はまだ明るいが、イルカは受付所にいるだろうか。 廊下の窓からアカデミーの大時計を見れば、間もなく午後3時を指そうかという所だった。 こんな時間に帰里できるなんて本当に珍しい。 木陰で昼寝でもしたら気持ちが良さそうだ。 そんなだらけた事を考えていたら、唐突に後ろから呼び掛けられた。 「カカシ先生!」 声の方を向くと、イルカが駆け寄ってくるのが見えた。 「お疲れさまです。これから報告ですか?」 はい、と返事をしている間に、イルカがカカシの隣に並んで来た。 「イルカ先生はこれから受付?」 「はい」 ただの返事に満面の笑みが付いていて、瞬間的にカカシの心拍が跳ね上がる。 果たして、カカシ以外の男は、この笑顔を見ても何とも思わないのだろうか。 いや、何かを思われて恋敵が増えるのは困るのだが。 「…ラッキーだな。イルカ先生の窓口に提出できるなんて」 まだ、こうしてさりげなく好意を匂わせる事ぐらいしかできない男にとっては特に。 「どの窓口でも同じですよ」 その言葉とは裏腹に、イルカは嬉しそうな顔をしてくれた。 こういう反応を見る限りでは、今の所、脈はあると思うのだ。 それに、こんな所で偶然出会うのも、イルカと縁がある証拠ではないのかと、自分に都合良く考えてしまう。 何より、窓口で顔を合わせるより、ずっと特別な感じがする。 そのせいか、もう何度も口にしている誘い文句が、今までにないほど滑らかに出てきた。 「良かったら、今夜飲みに行きませんか」 居酒屋で入浴剤を渡せば、イルカの笑顔を肴にできるだろう。 イルカの笑顔は、どんな酒でも最高級の味に変えてくれる不思議な力を持っているのだ。 「はい!えっと…6時半には終わると思うんで、それまで待機所でお待ち頂いてもいいですか?」 「わかりました。イルカ先生のお迎え、大人しく待ってます」 言ってしまってから、はっとした。 お迎えなんて言葉は今時、児童施設ぐらいでしか使わない言葉だった、と。 さっきまで一緒だった夕顔が子どものお迎えに行くと言っていたので、ついそんな言葉が出てしまった。 だが、それを聞いたイルカは楽しそうに笑っているだけだった。 どうやらカカシへの好感度が下がった訳ではなさそうだ。 ほっと胸を撫で下ろし、二人で和やかに談笑しながら受付所へ向かった。 |